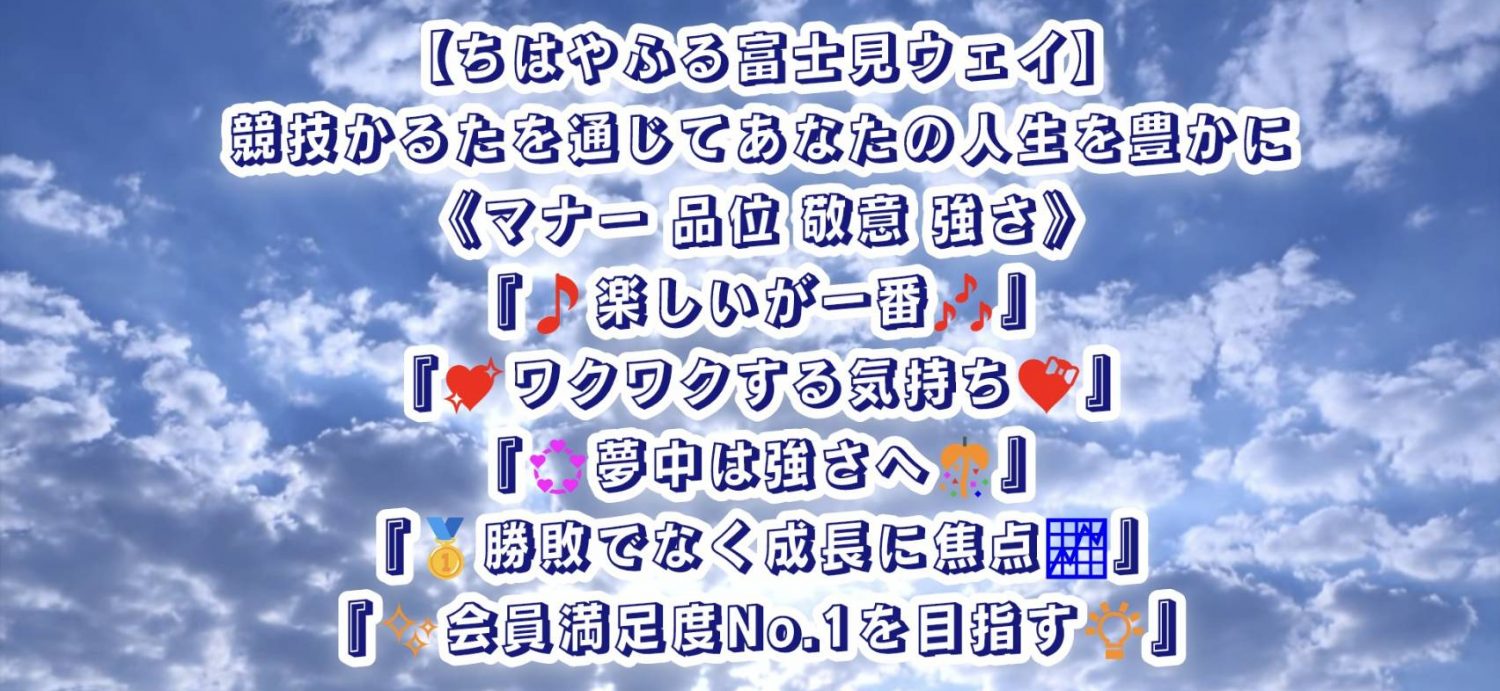会場となった東京の湯島天満宮(通称湯島天神)の参集殿。湯島天満宮は雄略天皇二年(458年)一月 創建。菅原道真公が御祭神として祭られており、百人一首にも道真公の句があります。「このたびは 幣も取りあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに」(このたびは ぬさもとりあえず たむけやま もみじのにしき かみのまにまに)
会場となった東京の湯島天満宮(通称湯島天神)の参集殿。湯島天満宮は雄略天皇二年(458年)一月 創建。菅原道真公が御祭神として祭られており、百人一首にも道真公の句があります。「このたびは 幣も取りあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに」(このたびは ぬさもとりあえず たむけやま もみじのにしき かみのまにまに)

会場となった東京の湯島天満宮(通称湯島天神)の参集殿。湯島天満宮は雄略天皇二年(458年)一月 創建。菅原道真公が御祭神として祭られており、百人一首にも道真公の句があります。「このたびは 幣も取りあへず 手向山 紅葉の錦 神のまにまに」(このたびは ぬさもとりあえず たむけやま もみじのにしき かみのまにまに)